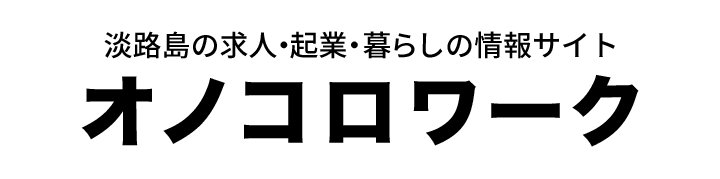食料自給率100%超え!淡路島の食の豊かさと暮らしやすさ…②
ポイント
・食の豊かさの源は3海に面した特殊な地形環境?!
(瀬戸内海、大阪湾、太平洋に面している、野菜が甘くなる、味わい豊かになる)
・兵庫県の畜産への意識の高さが食肉の質を上げている。
・島だったからこそ!地元に残る、地域に根ざした一次産業や二次産業。
(麺業、酒造、醤油蔵、牛乳、製塩。農業、漁業、畜産や養鶏も。)

どうして淡路島の玉ねぎは甘くて美味しいのでしょうか?!

島なので大規模農業ができず、島の農家さんの愛情がたっぷり含まれているから美味しくなるのです!という理由もあるかもしれませんが、甘くなる理由が諸説ある中では、東西の海風に土壌がさらされることで、甘みが増すのではないか?!という説が有力です!

スイカに塩を掛けると甘くなる!というのとは違うかもしれませんが、ミネラルが豊富に含まれてそうですね!

淡路島の玉ねぎの苗を他の地域で育てても、淡路島の玉ねぎのようには甘くならなかったという話もあるので、淡路島の栽培環境に理由がありそうなんです。常に海風にさらされていることや、全国平均と比較すると雨の日の確率が7割くらいしかない(晴れの日が多い)ことなどが影響しているんでしょうね!
淡路島は瀬戸内海、大阪湾、太平洋に囲まれていることから、獲れる魚の種類も豊富です。漁獲量はそこまで多くありませんが、四季折々に様々な魚を味わえることも魅力ですよね!

内海の島であるという特殊な地形が淡路島の食の豊かさにつながっているんですね!自然環境のおかげなんだなぁ!

自然環境だけでなく、お肉の美味しさに関しては兵庫県全域で畜産の質にこだわっている影響もありそうですよ!神戸牛(神戸ビーフ)に象徴されるように、兵庫県は牛だけでなく畜産の質へのこだわりは他県には負けない意識の高さがあります。

色々な環境に恵まれて、淡路島の食の豊かさが醸成されているんですねぇ!

環境といえば、大鳴門橋(1985年)と明石海峡大橋(1998年)が開通するまでは、淡路島は離島として生活や文化を育んできたため、地域生活のための一次産業(農業・漁業・畜産業)や二次産業(食品加工業など)が色濃く残っているのも淡路島の特長です。

離島だと「島の中で生活を完結できるように」となりますものね!農業も漁業も畜産も、島内の人たちの生活のために育んできたと思うと、地域のつながりの深さや、距離の近さを感じますね!

そうですね!他にも、麺業、酒造、醤油蔵、牛乳、製塩など、生活に根ざした食産業や食文化が残っているのも淡路島の魅力となっていますし、地域の食にまつわる資産と言えるかも知れませんね!
淡路島の製麺屋さんが合併して生まれた淡路麺業社では、今は生パスタを全国に提供するようになっていたり、淡路島牛乳も関西一円で親しまれるブランドになっています。こうした淡路島ならではの食産業は、島の外にも提供される時代になりました。これからも、続いてきた淡路島の食の豊かさに感謝して、後世に残していきたいですね!

ただ美味しいだけではない淡路島の食の豊かさを知ることができました。淡路島の食文化をもっと大切にしていきます!